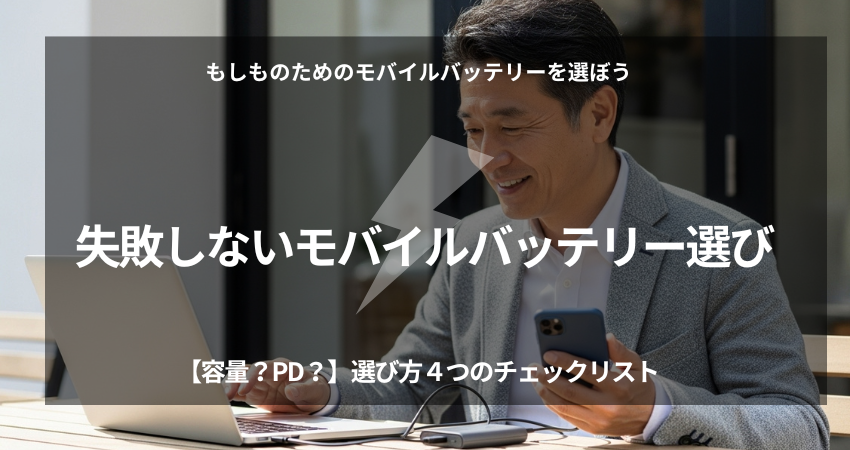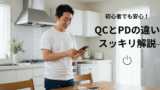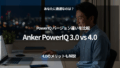「自宅で仕事をしているから、モバイルバッテリーなんていらないよね?」
そう思っている方は、きっと少なくないはずです。
以前の僕も、まさにそうでした。
便利そうだけど、電源に困らない家の中では「優先順位は低いガジェット」だと考えていたからです。
だって、家にいればスマホもパソコンも、デスクの下でいつでも充電できます。
だからずっと、モバイルバッテリーって「スマホを外でも積極的に使う人用ガジェット」くらいに考えていました。
僕自身、外に出るとそれほどスマホをいじることもなかったですし。
でも、ある日を境に、考えがガラッと変わりました。
僕たち世代こそモバイルバッテリーを「持っておくべき」だと心から思っています。
それは、毎日使うものではないけれど、”いざという時の安心”を買うツールだからです。
まずは、僕のリアルな失敗談から聞いてください(笑)
そして、一緒にデジタルライフの「安心」を一つ増やしていきましょう!
この記事でわかること
- 「いらない」が「必需品」に変わったリアルな失敗談
- 災害や仕事に備える!僕たち世代がモバイルバッテリーを持つべき5つの理由
- 「安全性」と「軽さ」で失敗しないモバイルバッテリー選びの4原則
- 【2025年最新】安心と軽さが魅力!おすすめモバイルバッテリー2選
「いらない」が「必需品」に変わった僕のリアルな2つの失敗談

普段は必要ない、そう思って油断していた僕が、心底焦った2つのエピソードをご紹介します。
どちらも、「持っておけばよかった…」と強く後悔した瞬間でした。
【旅先で心臓バクバク】写真撮影でバッテリー消耗!モバイルSuicaが使えない恐怖
家族旅行に行った時のことです。
もともと使っているスマホのバッテリーが少し弱っていたこともあり、旅行中は特に注意していました。
旅行先では、スマホがまさに大活躍。
美しい景色を撮る「カメラ」、次の目的地を調べる「地図ナビ」、そして電車に乗る時の「モバイルSuica」。
気づけば、スマホのバッテリーは残りわずか。
いよいよ帰りの電車に乗ろうとしたとき、スマホの電源マークが…ほぼ無い!
「もしここでバッテリーが切れたら、モバイルSuicaが使えない…」
慌てて改札でタッチしてみたものの、反応するかどうかで心臓がバクバク。
現金を持っていたので最悪は切符を買えますが、手間と焦りは計り知れません。
今、僕たちの「財布」や「切符」はスマホの中にあります。
そのスマホの電源が切れるということは、移動も決済もできなくなることを、身をもって痛感しました。
【仕事のチャンスを逃す?】出先でのクライアントからの電話とバッテリー20%の焦り
自宅から少し離れた場所で用事を済ませていました。
その日、うっかりスマホの充電を忘れてしまい、残量は20%ほど。
「でも、まぁ何もないだろう…」と楽観視。
そんなタイミングで、急にクライアントから電話がかかってきました。
もう急にバッテリーのことで頭はいっぱい。
急いで電話に出たものの、会話中、頭の中は「いつ切れる?もう切れるかも?」とバッテリー残量のことでいっぱい。話に集中できず、うわの空になってしまいました。
もし途中で電話が切れてしまったら、印象が悪くなるかもしれない。
そして、もし完全に切れたら、折り返し電話をしようにも、相手の連絡先すらスマホの中にあるから辿れない。
結局、電話は何とか持ちこたえましたが、「仕事の重要な局面で、たった1台のバッテリーに支配される」という状況は、本当に情けないし、準備不足だと反省。
外に出るときは、デジタルな安心も一緒に持ち運ぶべきだと痛感しました。
災害や仕事に備える!モバイルバッテリーを持つべき5つの理由

では、具体的に僕たちがモバイルバッテリーを持つことで、どんな「安心」が手に入るのかを見ていきましょう。
災害時、情報と連絡を止めないための「命綱」になる
停電や災害時、生活を支える電気が止まっても、モバイルバッテリーでスマホさえ生きていれば、次の行動がとれます。
- 家族や友人への安否確認
- 被害状況などの情報収集と共有
- もしもの時の仕事の連絡・納期調整
1台あるだけで、“もしも”を生活の中断にしないための、大きな保険になるんです。
▶ 災害(さいがい)時にもスマートフォン・SNS(エスエヌエス)を活用しよう(総務省)
モバイル決済・電子チケットなど「財布機能」を失わない保険
電車やバスに乗るモバイルSuica、お店でのキャッシュレス決済、コンサートの電子チケット。
これらはすべて、スマホのバッテリーに依存しています。
バッテリー切れは、「財布とチケットの機能を同時に失う」こと。
モバイルバッテリーは、あなたのデジタルなお財布を守る保険です。
旅行や出張での「時間の節約」
旅行や出張先では、写真・地図・連絡とスマホが大忙し。
「充電できる場所を探さなきゃ…」と焦る時間って、本当に勿体ないですよね。
モバイルバッテリーがあれば、充電の心配をせず、美味しい食べ物や綺麗な景色に集中できるし、たくさん写真も撮れますね。
家族やパートナーを助けられる「頼れる存在」になれる
家族旅行や外出時、お子さんやパートナーに「充電なくなった〜」って言われた経験はありませんか?
そんな時、サササーッ!とバッグからモバイルバッテリーを差し出せると、まさに憧れの“頼れるお父さん(お母さん)”になれます。
2ポートタイプなら、自分のスマホと家族のスマホを同時に助けられますよ。
「安全性」と「軽さ」で失敗しないモバイルバッテリー選びの4原則

正直、モバイルバッテリーは安いのを買うと後悔することがあります。
全然充電できなかったり、発熱したり…。
僕のように失敗しないために、これだけは押さえておくべきポイントを、わかりやすく4つにまとめました。
容量は「10,000mAh前後」がベストな理由
モバイルバッテリーには5,000mAhや20,000mAhなど様々な容量があります。
僕たち世代の普段使いとしては、10,000mAh前後が最もおすすめです。
- 10,000mAh:スマホを約2回分フル充電できます。災害時の安心感としても十分なラインです。
- 重さのバランス:これ以上大きくなると、重くて持ち歩くのが面倒になりがち。毎日持ち歩ける軽さとのバランスが良いのが10,000mAhです。
短時間でサッと!「急速充電(PD対応)」は必須レベル
モバイルバッテリーを買うなら、「PD対応」と書かれたものを選びましょう。
PDとは「Power Delivery」という規格のことで、簡単に言うと「とにかく速く充電できる技術」のことです。
PDについては以下の記事も参考にしてください。急速充電の詳しい記事です。
出先で充電する時、1時間も2時間も待っていられませんよね。
このPDに対応していれば、短時間でサッと充電を済ませられるので、時間の節約にもなります。
安全性は何より大事!「PSEマーク」と信頼ブランドをチェック
バッテリーが熱を持ったり、最悪の場合、発火したり…というニュースを聞くと不安になりますよね。
日本国内で販売されるほとんどのモバイルバッテリーには、国の定める安全基準を満たした証である「PSEマーク」がついています。必ず確認しましょう。
また、AnkerやCIO、エレコムなど、信頼できるメーカーの製品を選ぶのが安心への近道です。
毎日持ち歩けるか?「重さ200g前後」が理想の軽さ
どんなに高性能でも、重くて持ち歩くのが億劫になるようでは意味がありません。
目安として、200g前後(スマホ1台分くらい)であれば、バッグに入れても苦になりません。
この「苦にならない軽さ」こそが、いざという時に助けてくれる重要なポイントです。
【2025年最新】安心と軽さが魅力!モバイルバッテリーおすすめ2選
「どれを買えばいいの?」という方のために、選び方のポイントを全てクリアした、今おすすめの2つのモデルをご紹介します。
初めての1台に!迷ったらこれ「Anker Power Bank (10000mAh, 30W)」
【こんな人に最適】 信頼性と軽さ、速さの全てをバランスよく求める方
モバイルバッテリーといえば、やはりAnker(アンカー)。
その中でもこのモデルは、軽さ(約220g)と容量(10,000mAh)、そして30W急速充電の全てを満たした、「迷ったらこれ!」と言える万能モバイルバッテリーです。
しかも3ポートなので先ほどの「頼れるお父さん、お母さん」に5歩ほど近づきます!
初めてモバイルバッテリーを買う方や、安心感を最優先したい方におすすめです。
ノートPCも充電OK!最強の相棒「CIO SMARTCOBY Pro SLIM Cable 35W」
【こんな人に最適】 カフェ作業や出張が多く、PCにも給電したい方
手のひらに収まるコンパクトサイズながら、USB-C単ポート最大35W出力に対応しています。
スマホはもちろん、急な外出時にノートPCへも給電できるパワーが魅力。
このタイプはUSB-Cケーブルが内蔵されているので、新たに別のケーブルを持ち歩く必要がありません。
2ポート有りますので、こちらも複数充電可能です。
見た目もスタイリッシュで、デスクやカフェで使っていてもテンションが上がるし、充電中は残量がLEDで表示されるのもありがたいですね!
まとめ|安全性を買って不安をなくすモバイルバッテリーの選び方

スマホやパソコンの充電が不足する可能性はいつでもあります。そうなると、“いざという時”に困ることがある。
これは僕の実体験から言えることです。
モバイルバッテリーって、確かに毎日使うようなものではありません。
でも、「あってよかった」って思う瞬間が、必ず来ます。
停電、出張、飲み会、旅行、そして家族の外出——どれも日常の延長にあります。
「使うのは年に数回。でも、その数回で“買っておいてよかった”と思える。」
デジタルライフを止めないための安心を、このガジェット1台で備えておきましょう。